昨日、町を歩いていたときに以下のような会話が聞こえてきました。
「(私のことを指さして)あの子、この前挨拶に来た子だよ。」
「知らないな。」
まだまだ私の知名度は、高まってないようです。
頑張らねば。
昨日、町を歩いていたときに以下のような会話が聞こえてきました。
「(私のことを指さして)あの子、この前挨拶に来た子だよ。」
「知らないな。」
まだまだ私の知名度は、高まってないようです。
頑張らねば。
ここ最近、「人口減少」という言葉を多く見聞きするが、その「事象」「要因」について自分自身に対する確認の意味で整理しておきたいと思う。
1.「人口減少」のパターン
「人口減少」という「事象」について、大きく分けると以下の3パターンが考えられる。
・「少子化」による人口減少
・「人口流出」による人口減少
・「死亡率上昇」による人口減少
それぞれのパターンについて、記載する。
(1)「少子化」による人口減少
日本政府が使用する「人口減少」という言葉には、このパターンを表している。
現在の日本では、女性の出生率が「1.43人」(2013年時点)となっている。
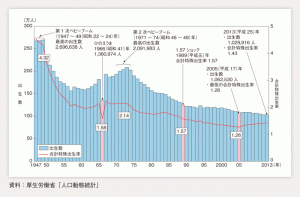
(厚生労働省「人口動態推計」より)
日本でこの出生率が続けば、日本全体の子供の数は減少を続け、総人口が減少する。
そのため、日本政府としては、出生率を高めるために「あの手この手」を使って対応しようとしている。
安倍政権の「1億総活躍社会」は、この「出生率低下による少子化」への対応策である。
(2)「人口流出」による人口減少
これは日本全体で発生しているのではなく、特定の地域で発生しているパターンである。(日本を出て外国に移住した場合、日本全体の人口減少となるが、他国へ移住する人の割合は少ないため、今回は省かせていただく。)
ある地域から「転出」し、他の地域へ「転入」する。
「転出」が、「転入」を上回ることで、この事象が発生する。
いわゆる「社会減」である。
(この「社会減」の場合、「人口が減少する地域」が発生する一方で、「人口が増加する地域」も発生することになる。。)
この「社会減」については、私の住む神流町のような「過疎地」では、ずっと問題とされてきた。神流町から他の市町村へと人口が流出し、神流町の人口は減少してきたのである。
日本政府は、この問題に対して「地方創生」というキーワードで対応しようとしている。
しかし、「社会減」への対応を行う場合、「地域間の人の奪い合い」へとつながることになる。
(3)「死亡率上昇」による人口減少
これは、人間が死亡することによって、人口が減少することを表す。
「貧困」や「物不足」によって、十分な栄養を取ることができずに死亡する。
また、「病気」等で死亡することも考えられる。
上記の部分は、自分で意図しない要因による死亡だが、「自殺」という自身で意図する死亡要因も見過ごせない問題である。
「自殺」については、環境や地域が関わるものなど、様々な要因が複雑に絡みあうため、対応策も特定の策を行うのではなく様々な策を組み合わせて行う必要がある。
2.自治体の状況について
(1)現時点で人口が増加している自治体
東京近郊の自治体では、人口が増加している地域がある。
これは、「交通機関の発達」や「仕事のやり方の変化」により、東京への通勤圏が拡大したことで人口が流入し、「社会増」となって人口が増加していると考えられる。
このような地域では、短期的に見れば「人口が増加している」ため、一見楽観的な将来を錯覚してしまう。
しかし、「出生率」で見ると、日本国内の人口が増加している地域であっても、「1.3~1.4程度」となっているため、「長期的には人口が減少する」状態にあることが分かる。
そのため、現時点で人口が増加している自治体においても、現状を楽観視することなく、「出生率向上」のための対応策を行い、「長期的な人口増加」に取り組まなければならない。
(2)現時点で人口が減少している自治体
現時点で人口が減少しているような地域では、「人口流出」という「社会減」が発生している。
また、「低い出生率」という問題は、日本国内全体で見られる傾向にあることから、人口が減少している地域においても同様に発生していると考えられる。
そのため、現時点で人口が減少している自治体においては、短期的には「社会減」に対する策を行い、長期的には「出生率向上」のための策を行う必要がある。
「長期」と「短期」両方の施策が必要なのである。
今回上記のように「人口減少」という言葉が意味する「事象」「要因」を整理したが、「事象」「要因」を整理するだけでは解決にならない。今後、また別の機会に解決策を具体的に考えていこうと思う。
今日は、挨拶周りの前に、神流町の12月定例議会の傍聴にも行ってきました。
今日は、初めて「一般質問」を直に見させていただきました。
「一般質問」のやり取りを見ていて、とても面白いと思いましたが、議員からの突っ込みに甘いところがあったので、「そんな回答で納得していいの?」と思うところが何回もありました。
特に、質問に対する町長の回答で「一生懸命努力する」という抽象的な表現を使っているところには、「具体的にどうするか示さなくていいの?」と、私はかなり疑問に持ちました。
神流町の町議会は、町のケーブルテレビで後日放送されます。ケーブルテレビでの放送により町民に見られてしまうことから、議会での突っ込んだ議論を回避しているようです。
議会は「儀式」のような場であって、実際の議論は、議会の前段の「委員会」で行われています。ただ、「委員会」でのやり取りが、住民に開示されていません。
私は、そのような状況がおかしいと思い、「委員会」のやり取りを住民に開示し、議会の場でも「もっと深い議論」を行うように変えていくべきだと思っています。
小池都知事がよくおっしゃっていますが、「プロセスの透明化」というのは、東京都だけでなく、どこの地域でも必要なことです。
今日は、万場(まんば)1区、2区の挨拶周りをしてきました。
今日で、神流町全地域への挨拶周り1周目が終了しました。
いろいろと試行錯誤しながら行ったので、1か月半がかかりました。
これまで挨拶周りを行う中で、大半の方々は「若者」が神流町に戻ってきたことに好意的な反応を示してくださいました。大変ありがたいことです。中には、私が伺ったときに不在だった方から、私の自宅宛に「お礼」の電話をいただくこともありました。電話をいただけると思っていなかったので、本当にうれしく思いました。
ただ、一部の方からは厳しいご意見をいただきました。このご意見についても、真摯に受け止め、今後の活動につなげていきたいと思います。
神流町全地域に挨拶周りを行ったことで、神流町のいろいろな面を見ることが出来ました。
また、私が思っていた以上に「高齢化」「少子化」が進んでいることも分かりました。
私は、「神流町に貢献したい」という思いから会社を辞めて故郷に戻ってきました。そのため、「高齢化」「少子化」に対して、本当に難しい問題ではありますが、逃げずに真正面から解決策を検討していこうと思います。
全地域への挨拶周りをさせていただきましたが、まだまだ神流町について知らないことが多いので、引き続き神流町について学んでいきます。
そして、神流町の住民の皆さんから頼りにされる存在になります。
今日は、生利(しょうり)、万場(まんば)地区へ挨拶周りに伺ってきました。
今日で、ようやく9割のお宅への挨拶が終了しました。
私は、中学卒業まで神流町で過ごし、高校から他の地域で生活していました。
挨拶周りをさせていただく中で、中学の頃までに行ったことのなかった地域にも伺わせていただき、これまで気づかなかった神流町を見ることができたと思います。
特に、私が中学の頃は、旧中里村との合併前だったので、旧中里村の地区にはほとんど訪問したことが無かったのですが、挨拶周りの中で伺うことができてよかったと思っています。
今後も継続して神流町の中を周りたいと思います。
今日は、柏木(かしわぎ)地区へ挨拶周りをしてきました。
高齢化率が56%を超える神流町では、尋ねる家の方々のほとんどが高齢の方です。
私が、いつものスピードで話をすると、聞き取りにくいようなので、高齢の方への挨拶のときは聞き取りやすくなるように、通常の話し方ではなく、「ゆっくり」「はっきりと」話すように心がけています。
相手に合わせて「話し方」を意識する必要があるのです。
東京で働いていたときは、「話すスピード」を意識することはほとんどありませんでした。
仕事でプレゼンをするときに、「ゆっくり」と話すことを意識したくらいです。
神流町に戻ってきてからは、高齢の方々と毎日お会いしているので、「話し方」を意識するようになりました。
環境が変わって、いろいろと変わってくるものだなと実感しています。
今日は、魚尾(よのお)、伝田郷(でんだごう)、麻生(あそう)地区の方々にご挨拶に伺いました。
今日でようやく神流町の3分の2のお宅に、ご挨拶に伺うことができました。
(ただし、タイミングが合わず、不在だった方もたくさんいました。)
私は、政治に必要とされる「地盤(家系が政治家とか)」「看板(知名度があるとか)」「鞄(資金力)」全て「ありません」。
また、私には「功績」や「実績」もありません。
そんな私でも神流町のお役に立てるよう、一人でも多くの方々にご挨拶したいと思い、挨拶周りを行っています。
この姿勢を忘れず、引き続き神流町の住民の方々へご挨拶に周ります。

今日は、群馬大学で行われた「群馬の未来創生フォーラム」に参加してきました。
初めて群馬大学の中に入ったのですが、15年前の大学生のころを思い出しました。
今日、「群馬の未来創生フォーラム」に参加した目的は、「地域おこしに関するヒントを見つけるため」です。
このイベントは、群馬県主催で行われたため、群馬県知事の挨拶が冒頭で行われました。
イベントは、1部が「内閣官房特別参与」による講義、2部が群馬県に住み様々な活動をしている方々のパネルディスカッションでした。
イベントで群馬大学の講師の方がおっしゃっていたのは、「群馬県は、18歳頃から進学等で若者が他県に流出し、そのまま群馬県に戻ってきてもらえないことが課題」とのことです。
性別ごとに比較すると、特に「女性のUターン率」が低いようです。
上記のような課題があるため、パネルディスカッションでは、「群馬のどこがいいのか?」「若者が群馬に戻ってくるには、どうすべきか?」ということが話し合われていました。
私は、37歳になってからUターンした身であるため、「俺の話も聞いてくれ」と思いましたが、今は何の肩書も無い状態なので発言することは控えました。
内閣官房特別参与の講義では、「地域おこし」としてユニークな取り組みをしている地域の紹介があったため、今後の神流町にも使えそうな情報を仕入れることが出来ました。
内閣官房特別参与としては、「現場を見ること」が特に重要とのことです。
「現場を見る」ことを、私も大事にしようと思います。
今日は、神流町の隣にある群馬県上野村(うえのむら)の村議会(12月定例議会)の傍聴に行ってきました。
傍聴の目的は、「神流町の議会運営方法との違い」について学ぶためです。
上野村は、これまで村おこしのために様々な取り組みを行っていることから、神流町よりも知名度の高い村です。
議会で印象に残ったことは、村議会の冒頭の上野村村長の挨拶です。
上野村村長は、「『地方創生』がブームとなっていることから、上野村へのIターン者数が伸び悩んでいる」とおっしゃっていました。
現在、国によって「地方創生」という言葉が用いられ、国家戦略として取り組まれていることから、これまで「先進地域」であった地域ではマイナスの影響を受けているのです。
日本の総人口は、頭打ちになり、今後減少が続きます。そのような日本社会の状況で、「地方創生」という言葉を使って地方自治体を国があおることは、「限られた人間という資源を、自治体間で取り合う」ことにつながっています。これは、「地方創生」の弊害です。
この「弊害」について、今日の上野村村長のお話から改めて気づかされました。
また、村議会を傍聴して気づいたことは、「議員から村長に対する質問がなかった」ことです。神流町の議会では、だいたい町長に対する質問が発生します。しかし、今日の上野村の議会では、村長に対しての質問が発生しなかったのです。村政の責任者は、村長なので、議員から1つくらい質問があってもいいのでは?と思いました。(今日は、村長に対する質問が、たまたま無かっただけかもしれませんが。)
議会と首長は、「いい緊張関係」を築いていくことが、地方自治に必要なことだと思うので、議会と首長とのやり取りをもう少し活発に行ってもいいのかもしれません。

写真は、上野村の「名誉村民」である黒澤丈夫さんの肖像画です。「40年間」という長期にわたって、上野村の村長をつとめ、「全国町村会会長」も行った方です。上野村役場の目立つ場所に飾ってあったので、写真に撮りました。
今日は、神ヶ原(かがはら)、魚尾(よのお)地区に挨拶周りをさせていただきました。
神流町は、平成15年に旧万場町(まんばまち)と旧中里村(なかざとむら)が合併してできた町です。
合併してから13年が経過していますが、いまだに「万場の人」「中里の人」という言葉が町民の間で使われることがあります。
また、現実として同じ町でありながら、「旧万場町の地区の人」と「旧中里村の地区の人」の交流が少ないということもあります。
このような「旧町・旧村意識」というものから、神流町が「ひとつの町」になりきれていないと、私は感じさせられます。
「旧町・旧村意識」は、「地域の文化・伝統を残すため」という意味で残っているのは良いと思うのですが、「私は万場の人だから中里のイベントに参加する必要はない」とか、町全体の協力関係の障害物として存在することは問題だと思っています。
(障害物としての)「旧町・旧村意識」を失くして、「ひとつの神流町」を作ることが私の目標です。
ここ数日の挨拶周りで、改めて「旧町・旧村意識」が存在することを実感しました。