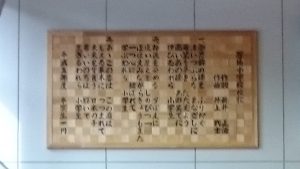1.本日の活動
今日(4月6日)の神流町は、終日曇りでした。
夕方には、時折雨がパラパラと降ることもありました。
最低気温は4度、最高気温は18.4度と非常に暖かくなりました。
今日は高崎市や藤岡市を行ったり来たりして、いろいろと挨拶にまわっていました。
2.国は「地方創生拠点整備交付金」の「選考基準の詳細」を開示し、「進捗状況」「KPIの達成状況」についても監視すべきだ
国により「地方創成拠点整備交付金」という制度が平成28年度の補正予算で創設されています。予算規模は総額「900億円」。この制度について、ざっくり言うと、国が、地方自治体からの申請された事業の半額を補助するというものです。申請といっても、すべての自治体の申請が通るわけではないようです。基準は「地方版総合戦略に計画された拠点整備で、利活用の方針が明確であり、波及効果が期待できる事業」とのことです。
「地方創成」という取り組みがが開始された当初、主に「ソフト事業」に支援の重きが置かれましたが、「ハード事業」(箱もの事業)に対する支援の要望があり、この制度が創設されました。
対象となる事業の半数は、今年の2月に決定しました。残りの半数は、4月下旬に決定予定とのことです。
私は、この「地方創成拠点整備交付金」について、国の基準・方針が不明確なように感じています。
①対象事業の選定基準・選定結果があいまい
内閣府は、選定基準として「施設整備の内容、施設の利活用方針、KPI等について評価」となっています。公開されている選考基準が、これしか記述されていないのです。内閣府の公開資料には、一部の特徴的な事例が掲載されていますが、採用された各事業において「どのようなKPIが設定され」「どの点を国が評価したのか」が公開されていません。これでは、「なぜその事業が採用されたのか」があいまいだと言っても過言ではないと思います。
本来であれば、採用された全事業に対して内閣府に提出された計画書を公表し、「施設整備の内容、施設の利活用方針、KPI」それぞれに内閣府がどう評価したのか公開すべきだと私は思います。内閣府には、選定した責任があるのですから、選定した基準を具体的に公開することも必要だと思います。
選定基準が公開されなければ、もし不採用となった事業が存在した場合に、「何が足りなかったのか」「どこを改善すればいいのか」「採用された事業は、どこが優れているのか」説明していないことと等しいと思います。
ぜひ内閣府には、当制度に採用された全事業に対して、「計画書」と「施設整備の内容、施設の利活用方針、KPIそれぞれに内閣府がどう評価したのか」を公開していただきたいです。
②選定したあとに国がどうかかわっていくかがあいまい
この制度に採用されれば、そこで「地方創成」が達成されたというわけではありません。この制度に採用され、その後、計画通りに事業が進められ、「施設整備の内容、施設の利活用方針、KPI」が達成されなければ「地方創成」に結びついたと言えないと思います。
しかし、内閣府から公表された情報では制度に採用された事業に対する「国の今後の関与」が明確化されていません。国には、制度を創設し、採用したのであれば、その事業を最後まで監督する義務があると私は思います。採用した時点で国の関与が終了してしまえば、この「地方創成拠点整備交付金」という制度が、単なる「お金のバラ撒き」で終わってしまい、「地方創成」が実現できたといい難いと思います。
民間企業であれば「KPI」が設定されていれば、「KPIを達成できたかどうか」を評価し、達成できていないようであれば、それに見合った処置(社内での評価が低くなる)が行われることが当然です。今回の制度では、「KPIの達成有無」に関する国の方針がまったく明記されていないので、国はそこを明確にし、「KPI」の状況を国が把握できるようにすべきだと思います。
ただ「お金を配布するだけ」という印象を与えかねない「地方創成拠点整備交付金」という制度。この制度で補助する「拠点」は、「ハード事業」(箱もの)であり、一旦作ってしまったら後世まで引き継がれるものです。作られた「ハード」が、「負の遺産」とならないよう、国からの「情報開示」と「継続した監視・評価」が行われることを切に願います。